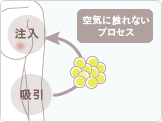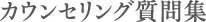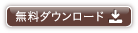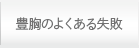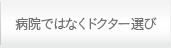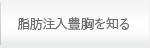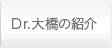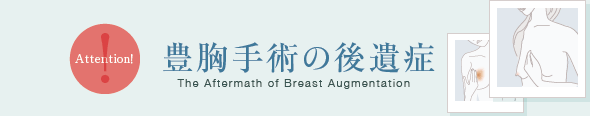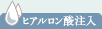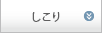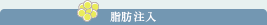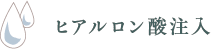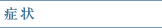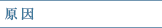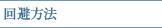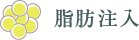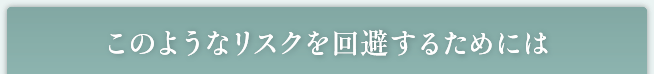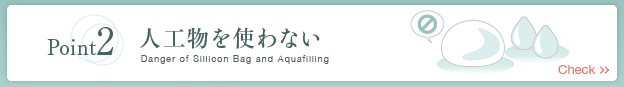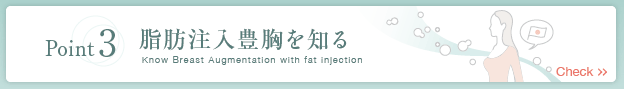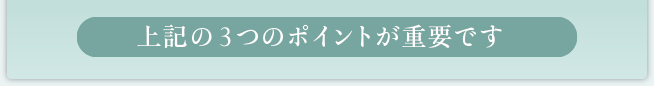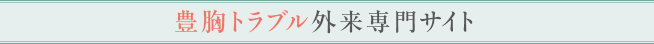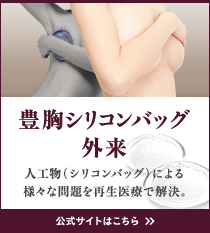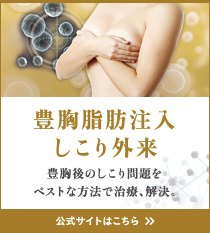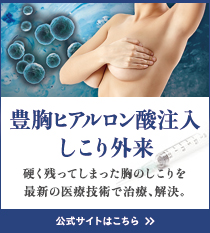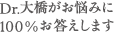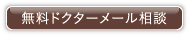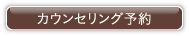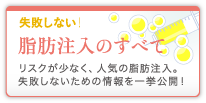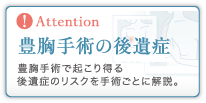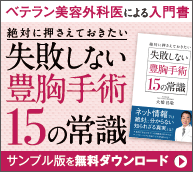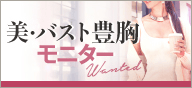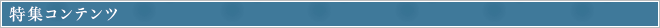
要因は様々ありますが、どの方法の豊胸手術であっても後遺症のリスクは考えられます。どんな後遺症があり、どうしたら回避できるのか、豊胸手術ごとにご紹介します。
触ったときの硬い異物感で気付く方が多いようですが、バストが部分的に盛り上がったり皮膚が引きつったりするなど、位置や大きさによっては視覚的に分かる症状も現れます。
また稀に、発熱や痛みを伴うケースも考えられます。
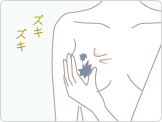
通常なら分解・吸収されるはずのヒアルロン酸ですが、1カ所にまとめて注入したり、分散してもその塊が大き過ぎたりすると、吸収しきれなかったヒアルロン酸が硬い被膜を覆い、しこりとして残ってしまうのです。
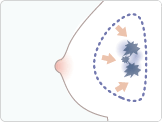
ヒアルロン酸が大きな塊にならないようにするには、持続性を考慮しつつも、しこりにならないような量を注入する、ドクターの技術の見極めが大切。
注入後であれば、軽くマッサージをして少しなじませるのもひとつの方法です。
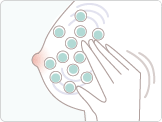
まず初期段階として、注意深く触ることでシリコンバッグだと分かるようになりますが、まだ柔らかさもあるので、不安もそれほどは感じないでしょう。
ただし徐々に硬さが強まり、ついにはバストも丸く盛り上がりテニスボールのように変形。ひどい痛みを感じるケースもあります。
![]()
シリコンバッグを包み込むように被膜が形成されるのは、体の正常な反応です。しかし、被膜が厚くなると、バッグが内に向かって締め付けられ変形。それに伴いバストも硬くいびつな形になります。
諸説ありますが、手術での出血量が多く炎症等を起こした場合に多い後遺症です。
![]()
シリコンバッグで豊胸した10人に1人は発症すると言われる後遺症なので、シリコンバッグを使わないのが一番の回避方法です。
クリニックによっては、術後に超音波トリートメントやマッサージ、内服薬での予防を試みるところもあるようですが、発症前に抜去するのが確実と言えます。
![]()
多少の硬さを感じるものの、目立った症状は現れません。ただし、この反応が強く出るとシリコンバッグの老朽化を早め、破損のリスクが高まります。
レントゲンや超音波検査、MRIやCTでは、バッグの周囲に白い影として確認できます。
![]()
シリコンバッグを包む被膜の周囲では常に小さな炎症が起こっています。体液中のカルシウムがこの炎症部分のアルカリ性に反応、卵殻のような結晶となり沈着するのが石灰化です。
日常的に炎症しているため、バッグを挿入したほとんどの方に起こり得ます。
![]()
石灰化は、シリコンバッグを挿入して10年以内には発症する確率の高い後遺症。そのため、バッグ以外の豊胸手術を選ぶ他、避けられないといっても過言ではありません。
短期間での入れ替えもひとつの方法ですが、体への負担が多大です。
![]()
この後遺症が発症すると、皮膚が赤くなったり痛みを感じたります。さらに悪化すると、変色したり水ぶくれができたり、化膿することもあり、皮膚が裂けてしまうという最悪のケースも考えられます。
![]()
シリコンバッグで血管が圧迫されることによる血流障害が原因と考えられます。
また、施設の衛生的な問題や、シリコンバッグに付着した細菌やカビで感染症を起こし、皮膚が壊死するケースもあります。
![]()
稀な後遺症ですが、施設の衛生面を確認しておくことをお勧めします。
血流障害は体型に対しシリコンバッグが大き過ぎると血管が圧迫されやすいので、適したサイズを選ぶことが大切です。
![]()
基本的には触って硬く触れるまで気付きませんが、バストの変形や皮膚の引きつりも症状のひとつ。また、痛みや発熱を伴う場合もあります。
脂肪注入が原因のしこりなら乳がんになることはありませんが、しこりの存在に気付いたらまずは検査が必要です。
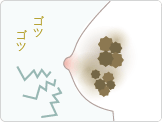
しこりの原因は脂肪が大きな塊で壊死することです。
その要因として、注入した脂肪に死活・老化細胞などの血液や酸素の循環を妨げる不純物が含まれているケースがあげられます。他にも1カ所にまとめて注入したり、注入量が多過ぎたりすると、脂肪は壊死してしまいます。

脂肪を塊で壊死させないために、まずは良質な脂肪を使用することが前提です。
そして、マルチプルインジェクション技術で皮下や乳腺、大胸筋内など、あらゆる層に分散させること。そして1回の手術の注入量が適切であること。個人差はありますが、片胸に約250ccが目安です。
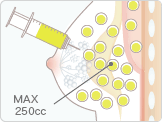
しこりだけでも硬い異物感がありますが、石灰化を起こすとより硬さが増したように感じます。また、しこりが大きくなったように感じる方もいるでしょう。
レントゲンやMRI、CT、エコーなどの検査では、映像や画像に白い影が映り込みます。
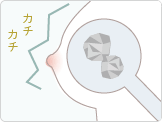
塊で壊死した脂肪は体に異物と判断され、被膜で覆われます。その周囲は日常的に炎症が続きアルカリ性になるため、体液に含まれるカルシウムが結晶となり沈着します。
炎症が誘因であるため、しこりができると高い確率で発症すると言えます。
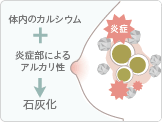
しこりを作らないということが回避方法となります。それには、不純物を除去した良質な脂肪を使用し、注入もあらゆる層に少量ずつ分散させ、また限度を超える量の脂肪を注入しないのがポイント。それを実行できるドクターを選ぶことが鍵となります。

この後遺症の症状には、炎症による痛みや腫れ、赤みなどがあげられます。また、発熱して熱がなかなか引かないことも。
さらに重度になると、周辺組織が化膿することが考えられ、見た目に分かる外傷が現れることも考えられます。
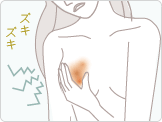
まず第一に、採取から注入までの間に脂肪が空気に触れ、細菌が混入(コンタミ)していた可能性が考えられます。
さらに、注入後に脂肪が塊で壊死してしこりとなった際、その細菌が増殖するとで感染症を引き起こすこともあります。
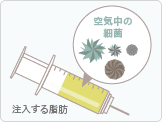
コンタミを回避するためには、衛生的な施設や、手法も空気に触れないプロセスのものを選ぶことが有効です。
また、脂肪を壊死させないことも大切。良質の脂肪を使い、適切な注入量を丁寧に少量ずつ分散させられるドクターを選びましょう。